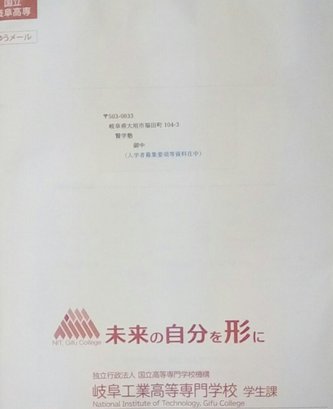高専からの案内
今年も岐阜高専さんから募集要項その他をいただいた。
いつもありがとうございます。
例年通り、10月初めには「進路指導のための説明会」も開いていただけるというご案内も入っていた。
だいぶん先のことなのでスケジュールが未定だが、今年も参加させていただく方向だ。
スケジュールが確定次第、申し込みをする。
この春はウチの塾から高専の受験者がいなかったので高専入試についてはあまり注意してみていなかったが、相変わらずの人気だった。
特に推薦入試への希望者が増加傾向にあり、建築学科では推薦入試の受験者の半分近くが落ちている(推薦に38人出願→20人合格)。
他の学科を見ても推薦出願者数=合格者数なのは機械工学科だけで、それ以外はすべて推薦でも不合格が出ているようだ。
高専は推薦入試の基準がはっきり数値化され公表されているので、希望者は中2のうちから内申点を強く意識して学習し、高い内申点を得ておけばかなり有利なのだが(公立高校と違って中1の内申点は加味されないかわり、中3の内申点が2倍になったりもしない)、このように推薦入試の倍率も上がってきており、(学科にもよるが)推薦基準を満たしても合格とはならないところに注意が必要だ。
推薦入試で確実に合格するためには、基準よりもさらに高い内申点が求められる。
他方、推薦入試で枠いっぱい(定員の半分)が埋まってしまうため、一般入試の実質倍率も上がる。
今春の場合、学科によって2.3倍~3倍(全学科合計で約2.6倍)ほど。
合格者よりも不合格者のほうがずっと多い、大学入試のような状況。
高専のホームページに掲載されている倍率は、推薦と一般をあわせた全体の倍率になっているので2倍程度になっているが、一般入試の受験者は推薦入試の合格者が決まったあとの残りの枠(各学科20~25人)を争うわけだから、現実はもっと厳しいということだ。
ご存じのように高専の入試問題は公立高校入試よりはだいぶん高度な内容だから、それなりの対策が必要。
一般入試でも内申点は加味されるので(これも数値化され、公表されている。配点にして約4割)、高専を目指すなら内申点が高いほうが何かと有利ということになる。
高専は入ったら5年間のびのびと学生生活ができ、共通テストだ、英語に民間試験導入だ、と迷走を続ける大学入試改革に巻き込まれる恐れもなく、卒業後も国立大学に編入学していく生徒も多いので、そういう先々の受験事情にピンとこない生徒本人よりも、保護者の方々のほうが魅力を感じているケースも多い。
だが、単位の認定は普通の高校よりも厳しく大学のそれに近いため、留年もある。
また、入ってからの進路変更が難しい。
工学系で学科まで細かく最初に決まっているため、本人の志向が変わったときには厄介なことになる。
私のように高校までの志が大学に入った後のちょっとした弾みでガラガラと崩れてしまった人間からすると、15歳で将来の路線を決めてしまうのはちょっと怖い気もしないでもない。
そのあたり、よく考えて選択をしてほしい。
高専側としても本人の強い希望で門を叩いてくれることを望んでいるはずだ。
こんなことを書きながら、今年の説明会で質問したいことがおぼろげに見えてきた。
忘れないうちにまとめておこう。