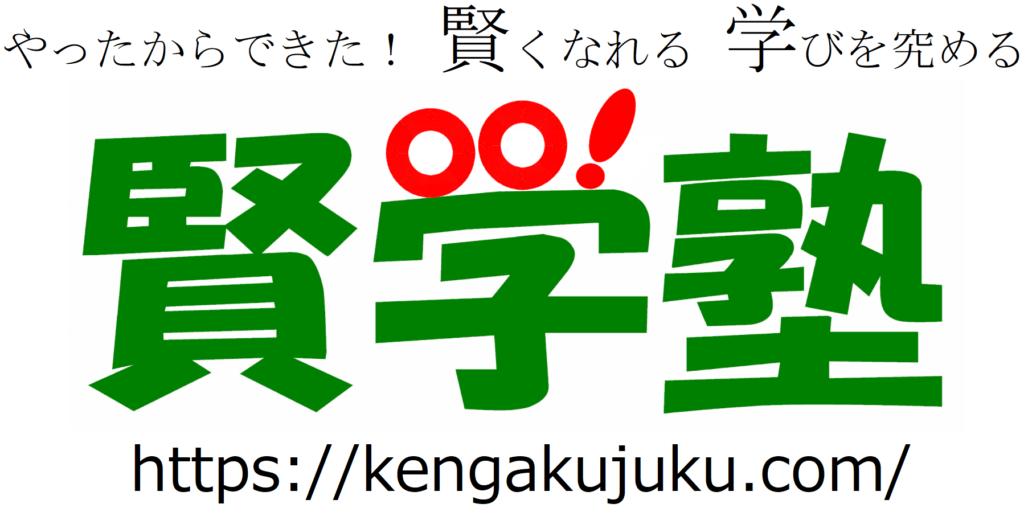北高130周年かあ。
朝刊を見たら、こんな記事が飛び込んできた。
大垣北高歴史つむいで130年 生徒がロゴ作成 他校と野球記念試合も:中日新聞
https://www.chunichi.co.jp/article/895925
そういえば以前北高のサイトでもそんな話を見かけたなと。
もちろん130年前は「大垣北高」ではなくて大垣中学(旧制中学)だった…と思って北高のサイトに行って確かめたら…
>1894年 岐阜県尋常中学校大垣分校認可。
と書いてあった。
できたときはまだ分校。
旧制大垣中学校ですらなかったのだった(今さら知る)。
岐阜高校はさらに古く、昨年で150周年だったはずだから、さすがというほかない。
それでふと岐阜高校のサイトにある沿革を見たら、
>明治13年07月30日 分校を安八郡大垣町に設け岐阜県第一中学大垣分校と称した
とある。
明治13年は1880年である。
つまりのこの場合の「大垣分校」は今の大垣北高の源流ではないようだ。
ネアンデルタール人が現在の人類の直接の祖先ではないというようなものだろうか。
高校を卒業してもう何年も経つが、今さら知ることが多すぎる。
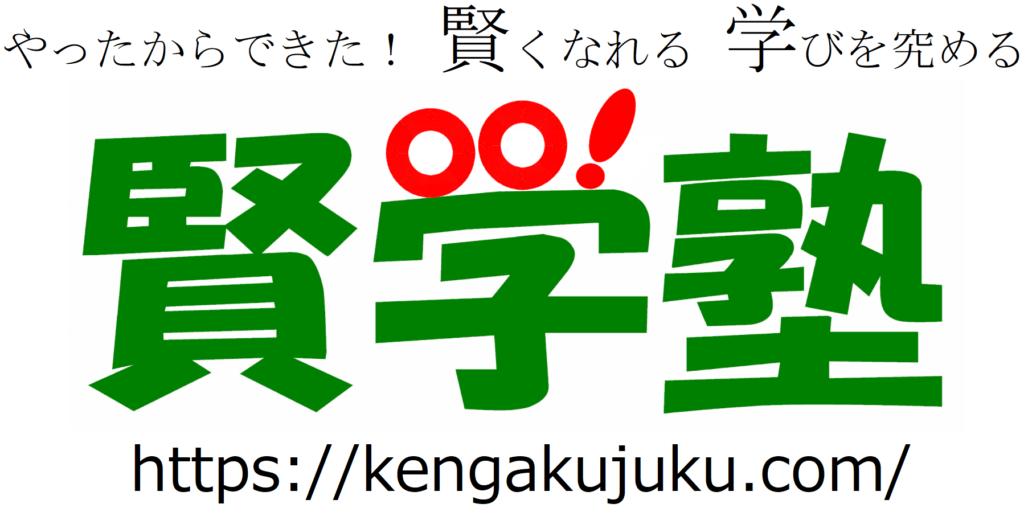
今さら知ると言えば5月1日が「名古屋大学記念日」(事実上の創立記念日)だったということをGW中に偶然見たネット記事で今さら知ったというか忘れていたというか何というか…。
言われてみれば大学生の頃「創立記念日だから5/1は休み」とかあった気がするが、覚えていない。
調べると2004年から名古屋大学記念日が大学の休業日から外されたという記事をネットで拾った。
ということは当然、私が在籍していた頃にはまだ休業日だったことになる。
「2005年入学だから知らなかった~♪」とかいう白々しい嘘はさすがに書かない。
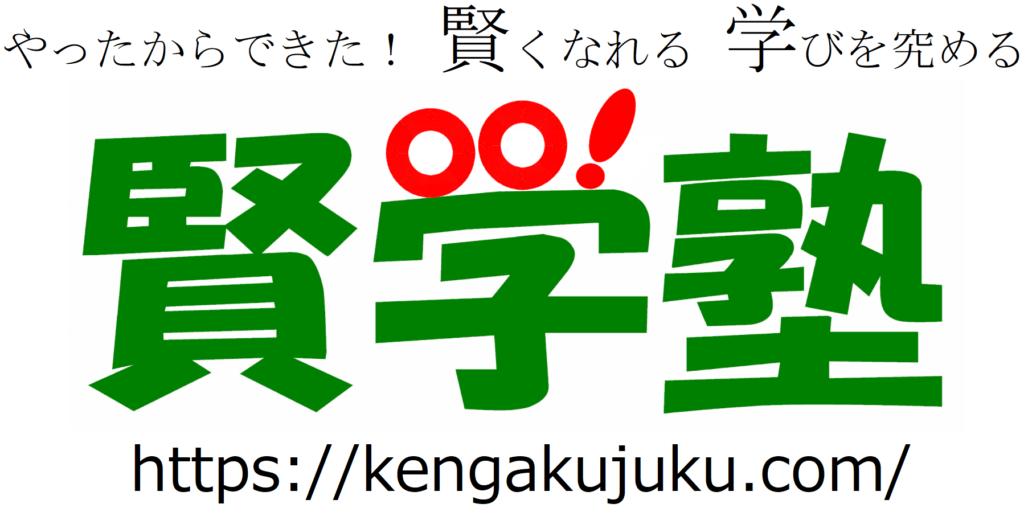
「名古屋帝国大学」は医学部だけでスタートして(この創立が5/1)、その後、理学部・工学部が増えて終戦を迎え、法経ができたのは戦後。
混乱期というか新制大学への移行期でまだぎりぎり「帝国大学」を名乗っていた頃だったと。
いずれにしろ、うちの大学で文系の各学部は隅っこのほうで小さくしている存在だった(だからといって別に自分個人が小さくなってはいたわけではないが)。
キャンパスの地図を見れば一目瞭然だ。
長年、官僚養成を担ってきた歴史から文系学部も比較的分厚い東大とは違う。
同じように理系学部の定員割合が圧倒的に多い(文系:理系=1:3ぐらいの)旧帝大仲間には九州大がある。
東北大と北大も似たようなものだ。
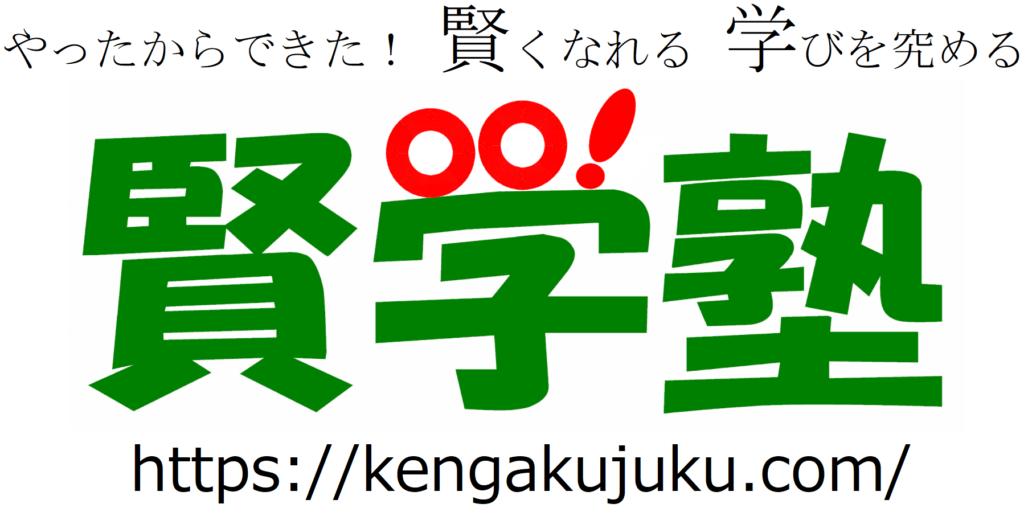
阪大も名大と同じような文理の構成で理系が圧倒的に多い、似たもの同士の大学だったはずだが…意外だった。
改めて調べたら阪大は文系の定員割合が4割ほどもある。
ええっと思ってさらに見たら阪大は学生数自体がずいぶん多い(東大とほぼ同じ規模。ということは国立大学で最大級の学部定員ということになる)。
はて?そんなにでかい大学だったかなと思ってしばらく考えて合点がいった。
21世紀に入り、阪大は大阪外国語大学を吸収合併した。
だから文系の人数が増えたんだなと。(単科大学とはいえ大学をまるごと1つのみ込んでしまったのだから当たり前だ)
わたしが若い頃に抱いた印象は、当時は間違っていなかったようだ。