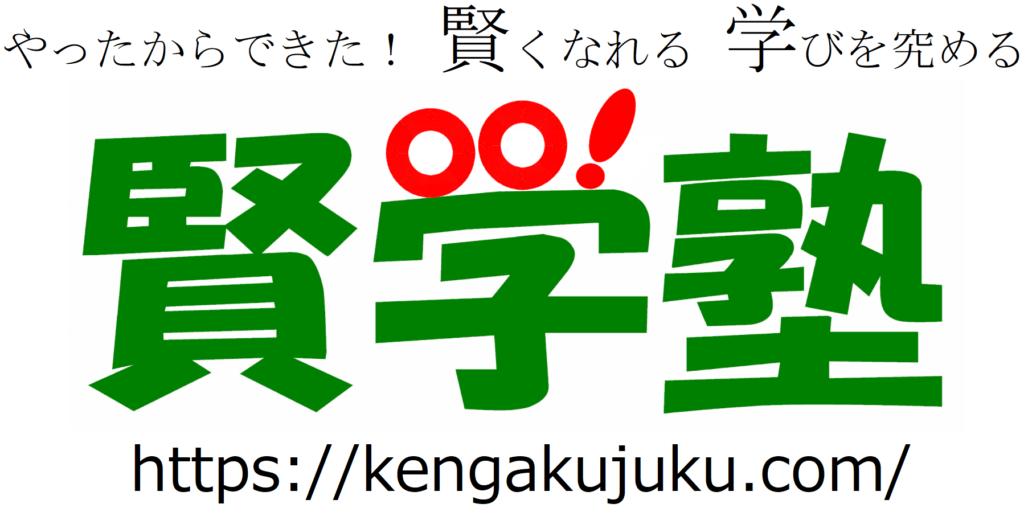昭和99年か。
そういえばちょっと前に「来年は昭和100年」とかいうニュースがあったなと思い出す。
昨日は昭和99年9月9日だったそうだ。
そんな話を昨日ネットで目にした。
だからどうだというわけでもないが。
そういえば私が子どもの頃は社会全体がまだ元号で呼ぶ方が主流だったために、公的な統計等の予測で未来を表すときに「昭和90年には~」とか「昭和100年には~」なんていう表現をしていた覚えがある。
一世一元の制なんだから「いくら何でもそんなに長く昭和が続かないだろう」と苦笑していた覚えがある。
今は未来の予測も2050年とか2100年とか、ほぼ西暦で言っているように思う。
「令和50年には~」なんて聞かない。
実際、昭和は64年で終わった。
といっても昭和元年は年末数日だけ、昭和最後の64年は年始の数日だけだったから、実質62年間ぐらいだったわけだが。
今の世の中、多くの人にとっては元号のほうが取り扱いに慣れないだろう(と私は思っているがどうなんだろう。少なくとも私はそうだ。少数派だったりして)。
塾の様々な文書も(お知らせから受講契約書まで)何年前だったか西暦表記に変えている(つまり開校当初は元号を使っていたということでもある)。
今年が令和6年だということに年の後半の最近になってようやく慣れてきたというぐらいのものだ。
といっても依然としてお役所は和暦が主であり、つまりは入試年度も和暦で表記されるから、元号にもある程度慣れておかないとミスをしかねない。
kengakujuku.netの過年度の出願状況のページや過年度入試の平均点のページに早見表を載せているのも、見に来た人の利便性の向上もさることながら、自分自身の確認のためというのが大きい。
「あの年はどうだったかな」と振り返るときに私自身あの表を見るのだった。
今日は2024年9月10日、令和6年9月10日、そして今の中3は令和6年度中学卒業生であり、彼らが受ける2025年春の入試の名前は令和7年度入試である。
とまあ、入試関係は和暦に加えて旧年度・新年度が交錯するので一層分かりにくい。
・・・だが、実のところ「きょう」と打つとPCなりタブレットなりスマホなりが「2024年9月10日」と変換したり「令和6年9月10日(火)」と変換したりするので、ふだん文章を書くときは自分の頭で考えなくても正確に打ててしまうのだった。
自分で考えないといけない。