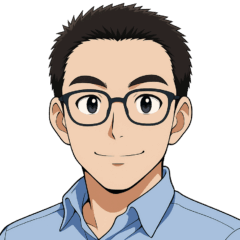明るく元気に間違えよう
間違えることは悪いことではない。
間違えた後、それをどうするかが大事。
この塾にずっと来ている子ならずーーーーーーーっと聞かされていることだし普段の対話・問答でも体感していることなので分かると思うが、初めての子にはなかなかそれが伝わらない。
特に学年が上になってからそういうことを徹底させるのは簡単ではない。
時間をかけてそうではないことを浸透させる。
この塾ができて二十数年、思えばずっと戦ってきた。
子どもたちの「間違えたくない」というか「間違えたという事実が残るのが嫌だ」という強迫観念と。
こちらは間違えてもいいと思っている(というか彼らが間違えたほうが私の出番がたくさんあっていいぐらいのものだ)し、間違えたことをきちんと記録に残してほしいので、なかなかかみあわない。
どんどん間違えよう。
最終的に間違えて困るのは、中学生なら高校入試本番のときだけ。
確かに高校入試本番について「どんどん間違えなさい」とは言えない。
間違いがより少ない方が高校に合格する。
だが、それ以前の(極論すれば)すべてのものは、テストであれテキストであれ何であれ「間違えてもいい」のだ。
間違いをそのままにしないことが大事なだけで。
間違いをやり直して、解き直してきちんと理解することが重要なのだ。
やり直しと言っても考えもなく単に答えを書いていても意味が無い。
考えないと解けないものは自分の力で解き直してやり方を理解することが大事だ。
しかし通い初めの子たちには・・・
1.答え合わせするときに暗記物でも無いのに赤で答えを書いて終わってしまう。
2.答え合わせをするときに消しゴムで間違いを消して正しい答えを書く。
3.やり方考え方は分かっていないが、こうじゃなければこうだろうと当てずっぽで答える(二者択一の問題に多い)。
ということが多い。
ずっと通ってきている塾生にはこんなことはまず起こらないのだが。
個別に対話・問答を重ねていると特にこういうことが浮き彫りになる。
中には分からないのに「分かったふり」をしてしまう子もいる。
問答を重ねるとそれが分かる。
おそらくそれまでの経験で、分かったふりをした方が得をする場面に多く出くわしたのだろう。
彼らなりの経験から生まれた「世渡りの仕方」「処世術」だったんだろうと思うと涙が出そうにすらなる。
少しずつそれらを解きほぐして、そうではないことを徹底させないといけない。
この塾は特殊な指導は(おそらく)ひとつもやっていない。
裏技その他テクニック的なことはほとんど教えていない。
「間違いをちゃんと直す」というごくごく基本的なことにこだわっているだけなのだ。
直すと言っても単に正答を書いてるだけでは意味が無い。
どうしてそうなるのかちゃんと分かって解き直す。
昔、芸人で「♪なーーーーーんでか」とギター漫談する芸人がいたが、私も対話問答しているとそんな感じだ。
(知らない人は「なんでかフラメンコ 堺すすむ」で検索!)
今度からギターを用意しよう(そうじゃない)。